今回ご紹介するのは、凪良ゆうさん 出版社 東京創元社『流浪の月』になります。
私たちがこの本と出会ったのは2021年6月、それから約1年後には実写映画として2022年5月13日に映画館にて放映されました。

こんにちは、”ゆみるも”です

夫婦二人でブログを運営しています。
・本書で出会う言葉や漢字を知ることができます。
・『流浪の月』がどのような小説なのかを少し知ることができます。
・私たち個人の感想を参考にし『流浪の月』を読むかどうかの判断材料にできます。
では最後までご覧ください。
『流浪の月』読んでみた感想

『流浪の月』と出会ったのは夜空の月が欠けた時と同時にスマホでメルカリを偶然にもタイトルが似ていたので購入したが始まりです。
本が届いたその日に読み始め、当日に読み終えるほど熱中したのを覚えています。
感想として言いますと、出会いはどうであれ、こういう形の愛もあるのだと思いました。
世間の目線からしてみれば、それはおかしいだろという人や変に感じる人もいると思いますが、それは彼女たちしかわからない事情や想いがあるのだと感じます。
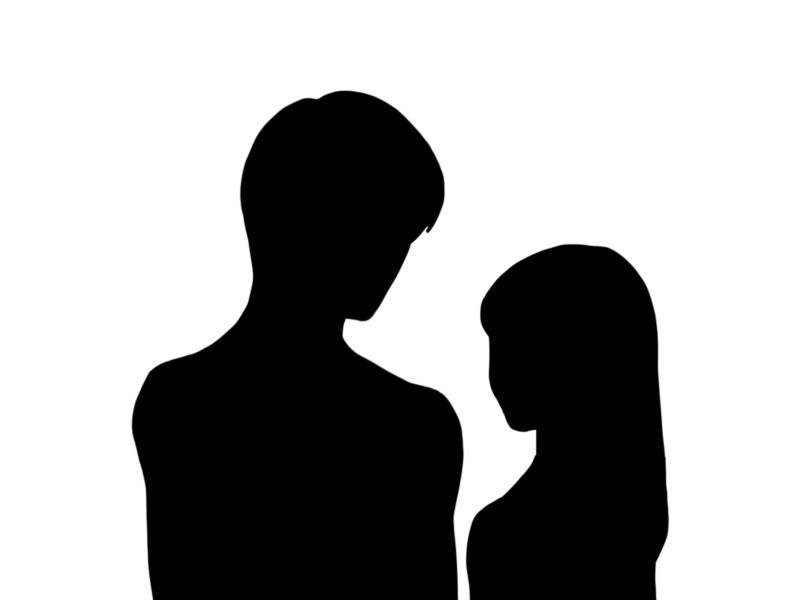
そんな彼女たちの複雑な家庭の状態や置かれた立場を本書でしることで前述にのべた意味が理解できると思います。
彼女たちの真実は彼女たちと読者しかわかりません。
ではほんの少しですが、本書に触れてみましょう。
できる限りネタバレにならないように表現いたしますが、それでも内容を知りたくないかたは、この見出しを飛ばして下さい。
『流浪の月』あらすじ

主人公の女の子は9さいの小学生、優しい父と自由気ままな母と三人で暮らしていました。
しかし、突然に父が亡くなり母はそのショックから立ち直れないまま、別の男と逃げてしまったのです。
主人公の女の子は、母方の叔母の家に引き取られましたが、叔母の息子が夜中になると女の子に嫌がることをします。
それがトラウマとなりこの家には居たくないと思うのです。

そしていつの日か主人公の女の子は、学校帰りに公園で暗くなるまで本を読むようになります。
その公園で同じように本を読む青年を見かけるのです。
ある日いつものように公園で本を読んでいると雨が降ってきました。
その雨にかまわず座っていると青年がそっと傘を差しだしてきたのです。
このときが主人公の女の子と青年、二人の運命のはじまりでした。

コチラの続きは本書でご確認ください。
『流浪の月』と出会った言葉や漢字
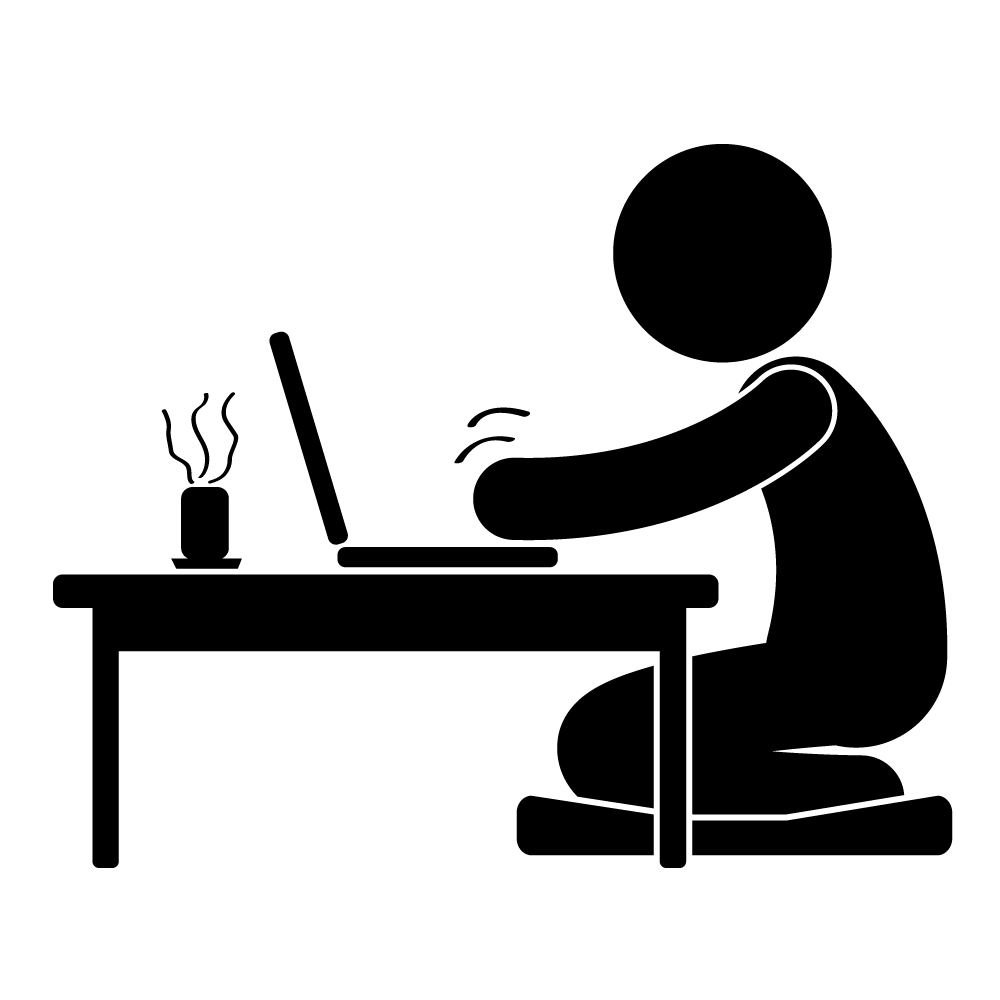
本書で出会った言葉をこの場を借りて、紹介しています。
出会ったというより、わからない言葉や読めない漢字などを調べて、ノートに記録しています。
ノートに記録しているだけでは、身につかないと考え、この場で紹介することにより、身につくと考えています。
本書で出会った言葉は、全部で4つの言葉や漢字でした。
そのうちの2つを紹介します。

今回は意外に少ないですね。
フェミニズム・・・1.女性の社会的、政治的、経済的権利を男性と同等にし、女性の能力や役割の発展を目ざす主張および運動。女権拡張論。女性解放論。
2.女性尊重主義。
goo国語辞書より引用
泡沫(うたかた)・・・1.水面に浮かぶ泡 (あわ) 。2.はかなく消えやすいもののたとえ。
goo国語辞書より引用
以上で2つ紹介しました。
今回は全部で4つと少ないですが、今後も継続してかわらず紹介していこうと思います。
まとめ

最後になりますが、2点ほど読み終えて思った事があります。
まず1点目は主人公の女の子、その身近な人たちは何故か彼女を不幸にさせる人が近寄ってきます。
例えば、あらすじで述べました叔母の息子の嫌がらせ、その他にもありますがここでは伏せておきます。
『流浪の月』だけではなく、他の小説にも生活環境が不幸と言う設定でそれに近づく人物もあまりよくない人が近づくというパターン、それが読者を引き寄せるのかなと思いましたが、なぜかスッキリしない部分でした。
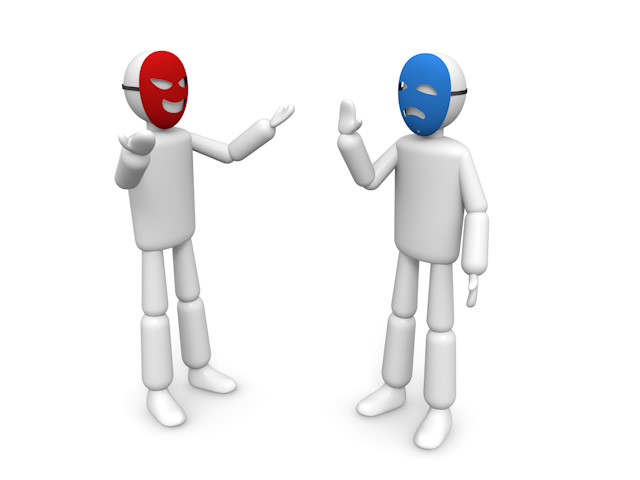
2点目は人々の記憶からは、彼女らの事を忘れるがネットは決して忘れないということです。
例えば、10年前に起きた殺人事件をネットで調べると被害者、加害者の名前は出てきます。
その場で出てこない場合もあると思いますが、深掘りすると家の場所までわかってしまうネット社会の恐ろしさにあらためて恐怖感を覚えました。
そして、恐怖感を覚えながらも自ら情報発信していることも忘れないように慎重に行動していくことを本書を通じて、考えさせてくれたと思います。
本書を一言で表すと

以上になります、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。

今後も”ゆみるも”をよろしくお願いいたします。
にほんブログ村
にほんブログ村




コメント